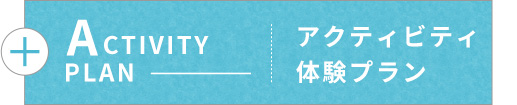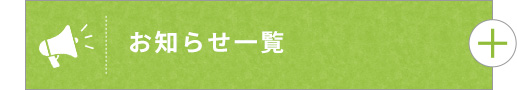- 2023.01.14
- 湯田川の未来を語り合う会
- 『湯田川の未来を語り合う会』は湯田川がもっと素敵で楽しく住みやすい町になることを目指す、湯田川住民会有志と東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科 湯田川スタジオによる協働プロジェクトです。現在は、湯田川樹木園〜由豆佐売神社一体で「みんなでつくる樹木園」プロジェクトを展開中。 湯田川スタジオは、一体どんな団体で、どのような活動を行っているのか?そして現在取り組んでいるプロジェクトの内容について、東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科2年の板垣 美里さんに伺いました。 Q「湯田川スタジオ」について教えてください。 私たちは東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科の学生です。スタジオ活動という授業の一環で2年生の前期から3年生の中期まで、湯田川地区でフィールドワークを行い、イベントを企画・開催しています。湯田川がもっと素敵で楽しく、住みやすい町になることを目指して、湯田川の魅力や困りごとについて話し合うなどの活動を2021年6月からはじめ、私たちで2期目となります。住民の方々とコミュニケーションをとりながら”よそ者である学生と取り組むからこそ出来ること”に挑戦しています。 12月、湯田川地区のコミュニティセンターで行われた会議の様子。 湯田川住民会有志とともに、イベントの企画を進めていく。 Q どのような活動を行っているのでしょうか。 毎月第2金曜日に湯田川地区でワークショップ・第4日曜日にイベントを開催しています。具体的には、由豆佐売神社と、そのすぐ脇にある樹木園をフィールドに「みんなでつくる樹木園」プロジェクトを展開しています。 湯田川といえば温泉地のイメージですが、実は温泉以外にもさまざまな資源が眠っていて、樹木園もそのひとつ。由豆佐売神社をふくめた樹木園の自然や歴史、文化を、整える・つくる・あそぶ・親しむ・知る・守る の6つの観点で次世代に受け継いでいきたいと考えています。 「竹細工」について、住民会有志に相談中。 将来的には、その地域固有の自然、歴史、文化などを野外で直接体験したり学習したりできる「フィールドミュージアム」となることを目指しています。「フィールドミュージアム」とは、地域全体が学びの場所となり、資料となるイメージ。町に訪れることで、博物館へ行ったときのようにわくわくしたり、発見があったり。より多くの人に知ってもらい、親しみをもてる場所にすることが目標です。 Q「みんなでつくる樹木園」プロジェクトとは何ですか? 「みんなでつくる樹木園」は3つの軸からなるプロジェクトです。 1つめは、のんびり歩ける樹木園づくりを目指す「整備サークル」。子どもや女性、観光客も歩きやすく気軽に利用できるように、湯田川樹木園の整備・清掃をします。 2つめは、親子で行きたい樹木園づくりを目指す「親子サークル」。親子にとって樹木園が思い出になるように、樹木園を使ってみんなでわいわい楽しい遊びをします。 そして3つめは、未来へつなげる樹木園づくりを行う、「樹木サークル」。樹木園の植物を使った工作や動植物調査を行い、樹木園に親しみを持ってもらうことを目指します。 「整備サークル」では、森を整えるために継続的な園内整備を続けつつ、段階を踏んで進めてきました。まずは不必要なものを取り除き、利用しやすい環境を整えていきました。具体的には、各所にあるベンチの苔を落とす、増えすぎた笹の除去、古い樹木プレートの除去、枯れている木の伐採などに住民会有志の方々と一緒に取り組みました。 伐採した竹で幻想的な竹灯籠をつくった。 Q その中でも、特に印象に残っている出来事はありますか? 11月に「整備サークル」の一環として行った由豆佐売神社の大掃除が特に印象に残っています。本殿までの階段の掃き掃除や、拝殿にある不用品の運び出しを行い、細かいところまでピカピカになりました。由豆佐売神社は湯田川地域に暮らす人々にとって、とても重要な存在。住民会の方々がひとつひとつを大切に扱う様子や、綺麗になって喜ぶ姿から「地元の人に愛されている場所だな」と伝わってきて…。外から来た私たちの活動を受け入れてもらえたことが本当に嬉しくて、やっていてよかったなと思う瞬間でした。 Q 今後の活動について教えてください。 2月の「親子サークル」では、湯田川神楽を見て学び、体験する活動を計画しています。ひとりでも多くの方に、湯田川神楽に興味関心を持ってもらえるよう、紙芝居やお面づくりを通して楽しい思い出になるような時間をつくれたらと湯田川住民会有志の方々に相談しながら絶賛準備中!実際に神楽の上演を見た後、オリジナルのひょっとこのお面や、箸置きをつくる予定です。 ひょっとこのお面 2月のイベントに向けた準備を進めているところ。 また「樹木サークル」では、樹木プレートの設置を計画しています。ただ樹木の名前を書くだけではなく、例えばプレートの形にこだわる、紅葉の時期を記載するなど、子どもたちが樹木園に遊びにいきたくなるような、好奇心をくすぐる樹木プレートをつくりたいと計画中。樹木園に訪れる野生動物のプレートや、植物のクイズを書いたプレートを設置する案もあります。さらに親しみやすい樹木園を目指して取り組んでいきます。 楽しそうに語る板垣さん。ワクワクが伝わってきます! 湯田川住民会と、「湯田川スタジオ」の若い力が合わさって、今まさに新しい取り組みが進んでいます。
- 2022.12.31
- モニター体験会冬〜報告コラム〜
- 秋。黄金色に輝く穂を刈り上げ、天日に干し、人の手で脱穀され仕上がった、お米と稲わら。そしてこの冬、湯田川温泉旅館協同組合では次なるプロジェクトがスタートしています。それは、湯田川の温泉で芽出しされたお米を使った日本酒の醸造。12月中旬、秋にも実施したモニター体験会の第2弾を開催しました。 ちらちらと雪の舞う日、参加者の皆さんにお集まりいただいたのは、湯田川温泉“芽出し米”を使った酒造りを委託している、鶴岡市大山で400年以上の歴史ある酒造「渡曾本店」。大山は最盛期には50軒を超える酒蔵が軒を連ね、「東の灘」と称されるほど酒造りで栄えた街です。 モニター体験会は、普段一般の方は立ち入ることのできない酒蔵の醸造工程の見学から始まりました。お酒に使われるお米は、食事用のご飯と違い、炊かれるのではなく蒸しあげられます。大きな蒸し釜から、かじかむほど冷えた冬の空気に、もくもくと湯気が立ちあがります。蒸しあがったお米は41~42度程度に冷やされ、麴室(こうじむろ)へと移されます。この麴室で種麴をふりかけ、52~56時間かけてお米のでんぷんを糖化させ、麴が完成します。この日は、生成途中の麴も特別に味見させていただきました。 麴は完成間近なものほど舌でその違いを感じるほど甘く、干し米のよう。参加者の皆さんも初めての体験に、「日本酒の甘い、辛いは温度管理によるものなのか?」など聞いてみたいことがたくさん。実際の現場を体験しながら杜氏さんへ直接質問できるなんて、酒好きにはたまりません。次は、この麴と蒸し米、水から酒母といわれる酵母を作るもとになるものを培養する様子を見学。 通常多くは乳酸を添加して1週間~10日程で酒母を育成する速醸(そくじょう)という方法が使われますが、今回湯田川温泉“芽出し米”で作るお酒は、自然にある乳酸菌の発酵を促して酒母を育成する生酛(きもと)造りで行われています。この方法は酒母が出来上がるまでに3週間ほども時間を要すると伺い、益々期待が高まります。そして、ここで造られた酒母を仕込みタンクへと移し、麴と7~8度まで冷やしたお米を3回に分けて入れていきます。 もう仕込み部屋は日本酒のフルーティーな芳香がしてきて、普段日本酒を飲まないという女性の方々もあまりの良い香りに、「今晩はちょっと飲んでみようかな」と。こうして酵母(糖)がアルコールへ変わり、日本酒となっていく様子を見学し、目の前で瓶詰めされた出来立てほやほやのフレッシュな日本酒を、今晩の夕食の席へお持ち帰り。最後には絞られた後の酒粕も見せていただき、酒蔵の体験ツアーは終了しました。 続いて向かったのは、こちらも大山にあり北前船で栄えた「善宝寺」でのご祈禱体験。「善宝寺」は龍神様をお祀りしたお寺で、海の生き物を供養するための五重塔があることから、漁師や海に関わる仕事の方の信仰を集めていることで有名なお寺です。 このご祈禱、ちょっと他とは違います。太鼓が打ち鳴らされ、15名を超える僧侶が一斉に読経を唱えながら、経典を次々にめくるさまは、まさにエンターテインメント。不謹慎かも…と思いながら、ついつい互いに「面白かったね」と言ってしまいます(笑) 冷え切った身体を芯から温める昼食は、何と言っても中華そばでしょう! 訪れたのは、鶴岡市 三瀬にある中華そば処「琴平荘」。湾状の海岸線の隣に建つ「琴平荘」は、もともと旅館を営んでいて、海水浴の閑散期にラーメンを提供し始めたのがはじまりなのだとか。2002年に中華そばの提供をスタートすると、たちまち大人気となり、県内外から人が訪れる名店に。あまりの評判で、現在は旅館を廃業し、毎年10月から翌年5月まで、約半年間の期間限定で開くラーメン店として、県内外問わずたくさんの人に愛されています。 日本海を望みながら、温かいラーメンをいただく。きっと最高の時間になるだろうと期待を胸に車から降りると、なかなか前に進めない…!?そう、冬の日本海は強風注意!風で前に進めないというのは、滅多にない経験かもしれません。夏には青くキラキラと輝く海が、真っ白に。 岩に波が激しくぶつかった際に生まれる「波の花」という白い泡は、極寒の海の風物詩です。 中華そばは「あっさり」か「こってり」の好みを選べるのが嬉しいところ。注文してほどなく、熱々の中華そばが目の前に!スープは鶏ガラベースに、魚介の旨味がきいたどこか懐かしさを感じる味わい。ツヤツヤもちもちの中太縮れ麺が澄んだスープとよく合います。ひと口いただくと優しいスープが冷え切った身体に沁みわたっていくよう。寒い冬にぴったりな、至福の一杯をいただきました。 手指も温まり、お腹もいっぱいになったところで、午後からは秋に刈った稲わらを使ったしめ縄づくり体験です。今回は参加者全員で1本のしめ縄を作り、湯田川温泉の守り神“由豆佐売神社”の大イチョウに奉納します。由豆佐売神社は、芽出しにも使われる温泉の泉源となる女神を祀る神社。その温泉によって芽が出て、たくさんの実りを与えてくださったことに感謝を込めて、しめ縄を奉納し、また来年の豊作を祈ります。早速わら細工の先生にご指導いただきながら、縄をなっていきます。 はじめに藁を柔らかくするために、(今回は)ビール瓶を使い叩いていくのですが、一斉に叩く様子が可笑しくて、自然と参加者同士の距離も縮まります。スタッフも含めた12名中10名が縄ない初挑戦という、ちょっと不安なスタートでしたが、お互いに教えあい、コツをつかんだ時には歓喜しながら、手を動かすこと1時間半!一人一人が作った縄をつなぎ合わせると、立派なしめ縄が完成しました! そしてお待ちかねの日本酒を楽しむ夕食会。一品一品、地元の食材と鶴岡ならではの郷土料理を味わいながら、午前中、直に瓶詰めされる様子を見てきた日本酒に杯を傾ける、他では決してできない体験です。先程まで一緒にしめ縄を作っていた一体感もあり、参加者同士も見知った仲のように和やかなひと時でした。 その宴を締めくくるのが、湯田川温泉に江戸時代から続く道化かぐら“湯田川温泉神楽”です。軽快なお囃子にのって出てきた獅子が、まるで生きているかのように踊り舞い、しまいには、どうなっているのかビールの一気飲みまで披露して客席は大盛り上がり。そこへやってきた“ちょんべ“とよばれるひょっとこが、また驚くほど表情豊かに獅子へいたずらを仕掛けては、追いかけられ、客席まで巻き込んでひと騒動を繰り広げます。誰もがこんな神楽、今まで見たことがありません(笑)この神楽は例年、土用の丑の日に行われる「温泉清浄祭」でお披露目されている由緒ある神楽。 湯田川温泉の時間軸には、温泉とお米とそれを祀る文化が流れています。この度のモニター体験会では、その一部を体験いただきました。春。4月に入ると、また新しいお米の種が温泉を産湯にして芽を出します。こうしてご参加いただいた皆様が、第二の故郷のように、湯田川の時間の流れに会いに来て下さる、そんな体験を届けたいと思います。
- 2022.09.15
- 湯田川温泉神楽を特別上演開催
- 湯田川温泉では下記の日程で湯田川温泉神楽を無料でご案内いたします。 【特別企画神楽スケジュール】 ■9/17(土)■ 20:00~ 正面湯前(雨天:九兵衛旅館ロビー前) ■9/24(土)■ 20:00~ 正面湯前(雨天:理太夫旅館2階宴会場) ■10/1(土)■ 20:00~ 正面湯前(雨天:仙荘湯田川3階宴会場) 「湯田川温泉神楽って何??」 湯田川温泉神楽は古くから伝わったものでありますが、江戸時代で最も平安であった、徳川三代将軍家光公の時代〈1620年代〉から、十二代将軍家慶公〈1850年代〉の天保年代頃まで盛大であったと伝えられており、庄内藩公酒井家にも年々藩主のお招きで藩邸で演じられた歴史ある伝統芸能です。 奏する音楽は、インド舞楽の形式をそのままに取り入れてあり、非常に珍しい音曲と評されています。 この神楽は、神社祭典に奏舞する神社神楽とつながりはありますが、その様子は異なり、里かぐらあるいは道化かぐらなどと称され、とても滑稽な趣があります。 湯田川温泉神楽は、藤沢周平原作 山田洋次監督の映画「たそがれ清兵衛」にも出演し、明るくユーモラスなお囃子がお祭りの場面を盛り立てました。(ロケは湯田川の由豆佐売神社で行われ、神楽保存会メンバーをはじめ多数の湯田川住民がエキストラとして協力しました) 湯田川温泉の記事を書いてもらっているすすきまきさんの記事はこちら この記事も素敵です(^_-)-☆ また、酒井家のご当主には旧御殿旅館に湯治でご滞在なされていたと聞きます。江戸時代から続く「湯田川温泉神楽」ですので、酒井家のご先祖様もご覧になっていただいたのではないかと推測しております。そこで当温泉地としても入部400年を記念し鶴岡市全体で観光を盛り上げていく所存でございます。 皆様お楽しみくださいませ。
- 2022.03.04
- 庄内一の“美酒温泉街”計画
- いま湯田川は、庄内一「日本酒が美味しい温泉街」として変化を遂げようとしている。 数年前からこの実現のため、宿の社長や女将らで行う日本酒勉強会の実施に取り組んでいるのが、つかさや旅館主人の 庄司丈彦さんだ。 庄司さんが日本酒に着目したのは、山形で“土地の酒”と言えば、ビールや焼酎などではなく “日本酒”であることから、他所から訪れる温泉客らに土地のものとして提供するには、日本酒が欠かせないと考えたことがはじまりだ。 宿側のオペレーションで飲料メニューは組まれがちだが、料理だけではなく日本酒で感動する瞬間を作りたい、湯田川のように小さな宿が多いからこそできると、働きかけている。 そうは言っても、日本酒はお客さんの好みもあれば酒の個性も様々で、更には料理も引き立てなければならず、そう簡単なことではない。 この日、地酒を使った燗酒の勉強会を開くというので興味が沸き、参加させていただいた。 集まった顔ぶれの7割が、なんと女将さんや仲居さん。 女性がメインということに「おっ、これは勉強会と称した旦那衆の飲み会ではなく、本気の勉強会だな」と、実は心の中で驚き、頼もしく感じた。 講師は新潟県からお招きした松本英資氏。 この方は2014年に廃業した「美の川酒造」の元社長で、現在は日本酒浪人として広く日本酒の魅力を布教している人気講師だ。 勉強会の中身はさておき、酒を囲んだ女性たちの姿勢は真剣そのもの。 やはりお客さんの多くは地酒を楽しみ訪れる方が多く、それぞれの宿でもここ数年、地酒の提供に力を入れているとのこと。 “日本酒”の表記を“地酒”に変えただけでもお客様の興味の反応が変わったと話す。 さて、地酒とは。 山形県内には51もの酒蔵があり、そのうちの18酒蔵がここ庄内にある。 秋田県境から新潟県境まで日本海沿岸に沿って広がる庄内地方は、鳥海山をはじめ月山や金峰山などの山々の恩恵により、肥沃な大地と豊かな水で“庄内米”の産地として有名だが、当然日本酒造りにも秀でている。 その山とそこから湧き出る水の個性だけでも庄内の酒はバラエティに富んでおり、まさにテロワールと言って良いだろう。 そこへ、海に山に里にととれる四季折々の食材を、手を掛け仕立てた料理の1品1品と掛け合わせたら、この上ない幸せだ。 講習が進むほどに女性たちの会話も弾む。 「秋田の方と福島の方では、好むお酒が違うよね。」 「お勧めをください、と言われると悩むのよ。」 「自分のとこの料理の味には、どんなお酒をお勧めすればよいのか…。」 「ぬる燗、熱燗、お客様が望むその違いが、今日の勉強会でやっとわかった。」 その一つ一つに、皆が頷く。 この日の勉強会で出された料理は、隼人旅館さんの寒ダラをメインに使用した郷土料理。 寒ダラは真冬の庄内のごちそうであり、寒ダラ汁はソールフードだ。 タラの昆布締めにタラと鱈子の煮物、寒ダラ汁。 あさつきの酢味噌和えや胡麻豆腐の餡かけと、どれもこれも庄内ならではの味覚であり、しかし、それらが「どうだ!」とばかりに出てくるのではなく、とても奥ゆかしく、それがまた何とも心地よい。 最近は食事なしの宿泊プランも多いが、こんな手づくりの郷土料理をいただきながら、地酒に舌鼓を打てれば、旅に来た甲斐があるというものだ。 いつか湯田川の温泉湯で芽出しした米で湯田川温泉独自の日本酒を作りたいと、庄司さんは言う。 米も魚も野菜も酒も、煮炊きする水もすべての水は繋がっているから、土地の料理には土地の酒が合う。 日本酒は難しい。 それでもこうして着実に、湯田川は庄内一“美味しい地酒が吞める温泉街”へと突き進んでいる。
- 2022.02.02
- “おとなの”企画持ち込み型 インターンシップ【飯野高拓1回目】
- 湯田川温泉観光協会では、皆さんがやりたい企画を応援することで地域に元気を分けてもらう、「企画持ち込み型」インターンシップを若干名募集しています。 ぜひご興味のある方はご応募ください。 この企画は観光庁の人材定着事業の一環で行いました。 交通費と滞在費は協会で負担、滞在期間の労働は時間給で支払い。 まず、どのような活動をしていただいたかをご紹介いたします。 参加者:飯野高拓氏(HP) 参加期間:令和3年9月8日~11日(隼人旅館に滞在) 参加スキル:プロフォトグラファー、情報発信コーディネート 還元内容:湯田川温泉内におけるフォトスポット創出、撮影データの提供、SNS情報発信アドバイス、協会員への撮影スキルアップ講座 ※プロボノタイプで参加していただきました。 飯野高拓 プロフォトグラファーの技術と経験を活かして、地域活性化に関わりたいと希望を頂いておりましたので、以下のことしていただきました。 スマホで綺麗な写真を撮るための講座、温泉街や旅館内でのフォトスポットの開発、情報発信へのアドバイスなど。 活動の記録はYouTubeチャンネル・IINO PHOTOをTご覧ください (由豆佐売神社 撮影:飯野高拓) 【実施内容】 「9月8日」 ・湯田川温泉にて打合せ ・湯田川温泉内散策&撮影 (夕暮れ時 撮影:飯野高拓) オンラインで打ち合わせはしておりましたが、 リアルでは初めてでしたので、協会の説明や飯野氏のスケジュールなどの確認をいたしました。 夕食前までずっと湯田川温泉内を回り、写真を撮り続けていただきました。 夕食後に意見交換した際にも、アイディアの芽が出てきました。 このあと12月に新しい湯田川の歴史情報発信が生まれます。 「9月9日」 ・湯田川温泉内撮影 ・撮影スキル講座 ・協会内での意見交換会 隼人旅館において、スマホ1つ持って撮影スキルアップ講座です。 今回のテーマは「自然光のみで撮る」というのがテーマです。 これが協会長である私(庄司)が指導前に撮った写真です。 飯野氏に指導後の写真。 スマホカメラの明るさ調整とピントだけでここまで変わります。 各旅館で、各々の課題を解決してもらいました。 厨房でできた料理の写真を撮るときははどうやって撮影すればよいか? お客様の記念撮影スポットはどこが一番適切か? などなど。 このように一つ一つを解決していただきました。 「9月10日」 ・SNS発信アドバイス ・湯田川温泉フォトスポット&イメージ写真撮影 最終日は湯田川温泉アンバサダーを務めていただいた「はるたま」さんにモデルになっていただき、 「30代女性の湯田川旅」をテーマにたくさんの写真を撮っていただきました。 我々では見えない視点を気づきがたくさん! はるたまさんがまとめてくれた動画もあります。 こちらからご覧ください。 このように、湯田川に滞在していただき新しい魅力の発信。 そして、我々のスキルアップに多いに貢献していただきました。 最後に、“おとなの”企画持ち込み型 インターンシップの2つのパターンを紹介して終わろうと思います。 【実現タイプ】 趣味や特技を活かして独立を目指している人向け。 ・これまで製作した作品で個展をしたい! ・手作り商品のポップアップショップを開きたい! などなど。 【プロボノタイプ】 専門的な知識やスキルを活かして地域貢献を行い人向け。 ・簡単に作れるポップの作り方を教えたい! ・旅館の経営コンサルティングを行いたい! などなど。 ぜひ、ご興味ある方はご連絡くださいませ。